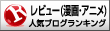『営繕かるかや怪異譚』は原作 小野不由美さん、漫画 加藤和恵さんの作品です。営繕とは、建物を新築したり改修すること。営繕屋の尾端が、怪異と人が共存できるように営繕する6つのお話が語られています。
第三話は『雨の鈴』。いくつかの角を曲がった袋小路に住む有扶子は、ある雨の日、小路の角に佇む喪服の女を見かけます。
ここから先は、ネタバレで、私なりにあらすじをまとめ、そのあと感想を述べています。ご注意下さい。

有扶子は昔からこの世のものではないものを見かけることがあり、喪服の女もそうだとすぐにわかりました。清らかな音の鈴を身に着けたその女からは、今までに感じたことのない悲しい気持ちを感じます。
有扶子が自分で見たことと周囲から聞いた話を総合すると、女は雨が降ると直線で進み、次の雨の日に、角で方向を変えます。そして、足を止めた真ん前に家の玄関があるとその家を訪ね、家人にお悔やみを言うのです。するとその家ではひとり、ひとが亡くなります。
次の雨の日に女が来るのは、袋小路にある有扶子の家。怯える有扶子の前に、友人である千絵が尾端を連れてきます。尾端は玄関と門の間に塀を作って女の向きを変えさせ、側溝に導く、と提案します。
雨が降り、有扶子は、側溝を通り過ぎていく女の姿を見かけます。恐ろしいもののはずなのに悲しく見えるそれがどこに行ったのかは、有扶子にもわかりません。

私が思うに、小野不由美さんはとても文章の上手な、巧みな作家さんです。小野さんの作品では、特に『屍鬼』を夢中になって読みました。私が不思議なのは、小野さんの作品って、読んでる間はどっぷりはまり込んで、完全にお話の世界に入ってしまうのですが、ページを閉じたとたん、まるで憑き物が落ちたみたいに「もとの世界に戻ってきた」感がするのです。だんだんに夢から醒めるように世界観が変わるのではなく、鮮やかな世界がくっきりと展開され、くっきりと終わる、それが小野さんの世界です。
加藤さんの表現は、小野さんの世界の広げ方とよくフィットしています。『雨の鈴』では、表紙と冒頭の5ページ、雨が降り、有扶子が喪服の女性を見かけ、鈴が鳴り、傘をさしかけようと思った有扶子が「声をかけてはいけない」と思うまでの描写で、しっかりと物語の世界に入り込ませてくれます。雨が傘に弾ける音や澄んだ鈴の音が聞こえるように、既にずぶねれの女の喪服が雨に叩かれてさらにじっとりと水を含んでいく様子が見え、匂いも嗅ぎ取れるような気がします。
そんな中で、これは声をかけてはいけないものだ、と有扶子が気づき、玄関の引き戸をピシャリと閉めることで、自分の鼓動も早くなってしまいます。加藤さんの作り出すドラマに、冒頭でしっかりと取り込まれてしまったのを感じて、どこかで興奮している自分もいるのでした。
繰り返し表現される、袋小路を俯瞰した絵にも感動します。袋小路について、加藤さんが「最初にイメージしていた図」と、ほぼ同じものを私も想像してしまっていたので、味わい深い日本の家屋が織りなす景色は本当に美しく、このような街に私も住んでみたい、と思いました。車があったら大変そうです。でも、車が通る道として描かれていなかったので、ここのご近所さんだったら、地区外に駐車場を借りることになるのかもしれません。絵で見るとロマンチックですが、遅刻しそうな朝などは、角がもどかしいかもしれません。他の作品でも日本家屋がしっかり描かれていて、営繕かるかやが活躍する素地がバッチリです。
角で方向を変えてまっすぐ進み、そこに面した玄関の中に入り、人の死をもたらす女が、独り暮らしの有扶子の家に来てしまったら何が起こるのか。家に入ってさえ来なければ害がなく、ただ悲しみを感じさせる喪服の女、というよりもその女がもたらす事象を想像したときの恐ろしさも、しっかり物語の中に封じられている私にとっては、自分ごととして恐怖を覚えさせられます。もう女はそこまで来ている。そんな中で、何ができるのだろう?
そんな恐怖に、尾端は営繕屋らしく、現実的に応えます。供養しようとか、対抗しようとかではなく「やりすごそう」。そしてやり過ごすための方法にも、営繕屋としてのセンスが光ります。普段の私だったら「女が何者なのか、やり過ごしたさきでは何が起こるのか」などと考えてしまうかもしれません。でも、小野・加藤ワールドの中では、やり過ごせたことでホッとし、「恐ろしいもののはずなのに悲しく感じる」有扶子の気持ちと降っている雨に、気持ちのいい重さを感じ、有扶子が創る見事な椿のアクセサリーを手にとってみたいとおもうのでした。
有扶子がアクセサリー作家である点も、古民家を改装したような千絵の店も魅力的です。原作ではどのように描かれているのか、原作も読んでみたくなりました。