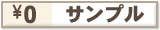『罰かぶり〜丸山遊郭哀史〜』は犬木加奈子さんの作品です。江戸時代から昭和まで存在した長崎の花街を舞台にした物語です。舞台はおそらく江戸時代の終わりか明治、清国の宦官たちがまだ力を持っている頃です。
銀波楼の女将は小さな子ども、阿蘭(おらん)に鉢を被せます。阿蘭は3年前の大火のときに倒れてきた柱に頭から潰された遊女から産まれたといいます。
ここから先はネタバレなのでご注意下さい。
女将は阿欄は罰かぶり(ばちかぶり)の子、顔を見ると災いをうける、といって誰にも阿蘭の顔を見せずに育てます。実は阿蘭は女将の妹分の遊女とオランダ人客の間にできた息子。男の子は丸山に置けないこと、外国人の血の入った子供の行く末が不安なことから誰にも見られないようにして女の子の下働きとして自分の手元に置いているのです。
物語は短編形式で、本当は美しい顔と金髪に不思議な目の色をした阿蘭の身の廻りで起きる遊女たちの泣き笑いが綴られます。
あるお話では子供の頃の阿蘭と出会った少年進ノ介に3年後の縁談の話が決まります。進ノ介とお雪は出会い、お互いに好意を持ちますが、進ノ介には心配事がある様子。進ノ介は阿蘭とも親しくなり、戯れに化粧をした阿蘭の素顔を見て美しいといいます。親しくする進ノ介と阿蘭を見て周囲は心配します。
3年後、縁談は一方的に破談になり、自分が出来損ないの男だから、と思った進ノ介は船に乗って異国に行きます。実はお雪は水痘であばたになってお嫁にいくのを諦めていたのでした。その後父の急死で家が没落してお雪は銀波楼への身売りを希望します。周囲はあんなあばたは遊女になれない、と指摘しますが、女将はお雪に同情して引き取ります。
お雪は阿蘭の顔を強引に見ます。進ノ介が夢中になっていた阿蘭を見てその性根を確かめたかったのです。阿蘭の美しい顔を見て優しい人柄に触れたお雪は「諦めがついた」と笑い、白無垢姿で女郎をすることに決めます。
その頃、洋行帰りの日本人で化粧が上手く、自分も化粧をしているという男性の噂が丸山に出回ります。それは進ノ介。阿蘭はどうやってか進ノ介を呼び寄せ、お雪と引合せます。進ノ介はお雪を身請けするといいます。戸惑うお雪でしたが、進ノ介が自分の化粧への情熱を男として後ろめたく思っていたこと、今の自分ならお雪のあばたを化粧で隠して美しくできると思っていることを打ち明け、ふたりは目出度く丸山を出ていきます。
いまこのお話は3巻まででていますが、後半では、インターセックスのお多加や、遊女になりたいと心から望む性格に難ありの醜女、お福なども主要人物として出てきます。お多加が中国からの宦官に見初められて中国に旅立っていくところで物語は終わります。

犬木加奈子さんはホラーの名手の1人です。私もRenta!を使い始めた頃、レンタルで犬木さんの短編集をかなりたくさん読みました。楳図かずおさんを始め、ホラー作家さんがコメディ作家としても活躍されているケースは多いと思いますが、犬木さんの作品にもコメディ要素があって、テンポよくお話を読ませる巧みな作家さんだと思います。
1987年にデビューされたということなので、この作品はデビュー後30年ぐらいでの作品になるのかと思います。作家さんも書きたいテーマがかわってきて、ホラーを描いていた犬木さんが、遊郭哀史を描かれるというのも感慨深いものがあります。
オランダ人と日本人の子供で金髪はないのでは、と思いますが、お話としては阿蘭が白人寄りの容貌をしているのはありだと思います。進ノ介が外国で阿蘭のような人にたくさん会ってきたと言っているので、かなり白人寄りなのでしょう。
銀波楼の女将はすごく優しいひとで、花街にこんなに優しい女性はいないだろうとは思ってしまいますが、彼女の優しさがこの物語の根幹となっています。そう、遊女の「哀史」といいながらも、この物語には人情が溢れています。美しい阿蘭も、あくまで自分を罰かぶりだと思って生きています。ちょっと様子が変わってくるのは醜女の遊女お福がでてきてからです。
まずは2巻ででてくるお多加の話から振り返ると、銀波楼のおかみはいかにもいわくありげなお多加を引き取って、大変なんだろうなあと想像がつくのですが、そんな女将だからこそお多加はここに置いていかれたのかなあ、と思います。
インターセックスの人物を描いた衝撃的な作品としては山岸凉子さんの『キメィラ』があります。そこではインターセックスの人物は、人を愛せず、動物や植物に溢れる愛情を注ぎ、孤独老人を襲って襲撃先の風呂場で洗濯までしてゆく、サイコパスとして描かれていました(記憶で書いているので、間違っていたらごめんなさい)。『キメィラ』は1984年の作品です。いまならば、インターセックスに対して誤解を生むとして避けられるべき表現とされるかもしれませんが、この作品に受けた衝撃は強すぎて、私がインターセックスを描いた少女漫画を読んだ時にこの作品に触れずにいるのは難しいです。
お多加はインターセックスであることを理由に見世物小屋に売られ、下半身を客に見せることで生活していました。その暮らしはお多加にとってはとてもつらいことでしたが、母である代吉は娘だけを売ることはせず、自分も股を開いて客に見せ、的としてタンポンを投げさせるという生活をすることで、娘を手放さず一緒にいることを選んだのでした。そして、女将ならお多加を悪いようにはしないだろうという目論見で女将の手にお多加を渡すという、実は哀しくも愛情のこもったお話なのでした。
しかも、お多加は本当の愛情を注いでくれる人に出会って、その人のもとで生きていく人生を選びます。その後の清朝の運命を考えると、お多加がいつまで幸せに暮らせたかはわかりませんが、少なくとも、丸山からは幸せを掴んで抜け出します。
そんなお多加に、阿蘭も愛情をかけます。後からきたお福は自分が性格が悪いことも醜女なことも自覚せず、人から諭されても信用せず、阿蘭を男として意識して、お多加に嫉妬するような少女です。でも、そんな図々しいお福のことも、犬木さんは愛情を持って描きます。醜女だけれど名器で男を喜ばせ、1日にどれだけ客をとっても構わない、と遊女の生活を楽しむお福を、阿蘭は気に入っているといいます。
阿蘭のお福への興味は、お多加へのものと違ってどこか超絶したところから俯瞰して突き放しているように私には見えてしまい、この物語を遊郭哀史であると同時に人情者としてここまで読んできた私にとってはちょっと違和感のある不思議な物語になっていました。
阿蘭は美しい青年になり、体格もどんどんよくなっていって、罰かぶりでは通用しなくなっていくのでしょう。これからは菊之助と名乗って生きていくようです。愛し合う宦官と一緒に清に渡ったお多加はよいとして、お福はこれからどうしていくのでしょう。
遊郭哀史といいながらも、いいひとたちが集い、生活を紡いでいく不思議なお話でした。