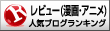『ミギとダリ』は佐野菜見さんの作品です。双子のミギとダリは、1990年、神戸市北区のオリゴン村の老夫婦のところに養子として入居します。しかし二人は夫婦の前では一人の少年を装い、秘鳥と名乗っています。
ミギとダリがこの街に来たのには理由があります。
ここから先は、完全ネタバレで、私なりにあらすじをまとめ、そのあと感想を述べています。ご注意下さい。

二人がこの街に来たのは、ここで亡くなった母の仇をとるためです。覚えているのは母(メトリー)の亡骸を埋めた丘とペイズリー柄の壁紙。二人は柄を迷路に見立てて遊んでいました。
ペイズリー柄の壁紙の家はこの街のどこかにあるはずです。ミギとダリは各家に入り込むため友達をつくることにします。そうして人の家にはいりこんではペイズリー柄の壁紙を探していた二人は一条瑛二という少年の家が目指していた家であることを発見します。瑛二に近づくため、秘鳥(ミギとダリ)は学校にも行きます。
ミギとダリは瑛二の家に秘鳥として入り込むことに成功します。二人は、5歳の頃の瑛二が、2階の窓に上ってきたメトリーを突き落としたことを知ります。そして、瀕死の重傷を負ったメトリーが、ミギとダリのいる場所に戻ろうとしている途中で命を落としたことに気づきます。母に捨てられたわけではなかったことに心を温かくします。
しかし、母の死の秘密は瑛二だけではないと感じた二人は、さらに探っていきます。一条の家で狂っていたのは瑛二ではなく、母の怜子だったことがわかります。若かった怜子は、さらに若かったメイドのメトリーに憧れられます。二人は親密な関係を築きますが、自分が子供を産めない体だと知った怜子は心を病み、自分の代わりに子供を産むようにメトリーに依頼します。夫もメトリーも心を病んでいきます。
メトリーは子供を3人産みます。ミギとダリ、そして瑛二です。
怜子は、その話を聞き出したミギとダリ、夫と娘、ミギとダリの友人である丸太を部屋に閉じ込め、瑛二と二人で生きていこうとします。しかし瑛二は怜子を殺し、家に火を放ちます。
もうだめだと思ったとき、ミギとダリのもう一人の友人、秋山が助けに現れます。ミギとダリは怜子とともに死のうとしていた瑛二を助けます。不様に生きさせること、それが、母を死なせた瑛二に、ダリが課した復讐です。
そして、ミギとダリは、老夫婦のもとに戻ります。老夫婦は、秘鳥が、一人ではなく、ミギとダリという二人の少年だったと見破り、二人を受け入れます。
少し時が経ち、瑛二が老夫婦の家を訪ねます。瑛二の父と妹、丸太と秋山も集います。瑛二はメトリーの墓碑も訪ねますが、自分の母はそこにはいないと言い、スッキリした様子の三兄弟。
その後、ダリは一人で進学校に旅立ちます。見送るミギ。二人はそれぞれの夢に向かって進むことにしたのです。

不思議な空気で物語は始まります。ミギとダリが何故秘鳥として老夫婦の前で過ごそうとしているか、その理由もわからないし、彼らが何故そうまでしてこの家にたいあもわからないことが、軟体動物っぽい二人のルックスとも合わせて、なんとも言えない独特な雰囲気を作っているのです。
ミギとダリは、老夫婦に気に入られるため、いろんなことをします。老夫の夢が、息子を肩車することなものの、老夫にそれだけの筋力がないと気づいた二人は、木とロープを使ったアクロバティックな動きでその夢をかなえます。また、老妻が、秘鳥と一緒にチェリーパイを焼きたいといえば、二人で器用にパイ皮でバスケット編みを作ったりします。
明らかになにかを企んでいるミギとダリ、犬のことを「ケモノ」と呼んだりする一風変わった会話、老夫婦に「二人いる」ことがバレないようにすりためのアクロバティックな動き。そういったものが混然一体となって、ミステリーともコメディともつかない独特の空気が生まれて、あっという間に作品に惹き込まれてしまいます。
思春期の少年のか細い肢体も、その空気をつくるのに一役買っています。老夫婦はアメリカ人なのかと、最初はちょっと悩んでしまいました。神戸のオリゴン村って、モデルがあるのでしょうか?根っからの北関東人である私にはちょっとわからないのですが、部屋や建物の雰囲気も食卓もアメリカンで、それも華やか空気を作品に添えています。
ボーイスカウトに入って、友達ってどうやって作るんだろう、となやんでいる様もおもしろかったです。どちらかというと、単調な感じで、シュールな笑いを含みつつお話は進行するのですが、単調な感じといっても退屈とはほど遠いのです。心底人がいい老夫婦と、なにかを企んでいるとはいえ、その思考は少年であるミギとダリのコントラストが、ユニークな陰影をつくっています。家を出てボーイスカウトに行ったり学校に行ったりしている間に、女装したダリがミギに惚れられたり、ダリがそのことをミギに勉強させていい成績をとらせるための材料につかったりしているうちに、気づくとどんどん話が進んでいるのです。
ちょっと単調、と思っていた物語の流れが、動いているように感じるのは、多分、ミギとダリの目的がわかってきたからだろう、とは思うのですが、どこかで明確に流れが早くなっていくのを感じるのではなく、気づいたらどんどん流れている感じがとっても新鮮でした。
キャラクターも、最初はミギとダリがあまりにもインパクトがあるので集中してしまうのですが、家政婦のみっちゃんが出てきたあたりから、すべてのキャラクターが魅力的すぎることに気づきます。そうすると、先を早く知りたい、という気持ちはもちろんあるのですが、それ以上に、その場その場でのキャラたちの動きや表情をじっくり楽しみたい、という気持ちが湧き上がってきます。
ミギとダリが、もう自分たちだけでは前に進めないと感じ、友人の秋山に、自分たちが秘鳥ではなく、ミギとダリという双子であることを打ち明けるところでは、お話が、引き戻せないところまで進んだことを感じます。それまでは、二人が秘鳥であろうとするシュールさを楽しんでいたのですが、秋山にミギとダリであることが知られ、秋山が丸太にその秘密を共有するところで、読者として楽しむべきポイントも変わったと感じるからです。どういう視点で楽しむのか、というスタンスを、自分が決めるのではなく、お話にきめられえうようで、とっても新鮮な気がしました。
瑛二の妹がまさかの丸太に惚れるところも面白かったです。ミギもダリも瑛二も秋山も恋愛に進むことがない中で(ミギはダリの女装姿に惚れましたが)、この二人の少年少女の間に恋愛感情が芽生えるのが面白かったです。妹も相当変わってる子なので、その妹が、美しい双子には目もくれずに丸太に感情移入するのが面白かったです。
怜子とメトリーの関係はホラーでした。怜子も変わった女ではあるのですが、二人の関係が支配者と隷属者だったものから、メトリーが優越感を抱いた瞬間の描写が怖くてゾッとしました。もともと独特なカラーを持つこの作品にさらに色が加わった感じでした。
シュールなコメディ?ミステリー?として始まったこのお話の中で、意外にも読者はミギとダリの成長を見出し、最後には二人の未来を祝福する、爽やかな気持ちでページを閉じることになります。
1巻の表紙のミギとダリに、どこか不穏な引っ掛かりを感じて興味を持ったこの作品でしたが、全7巻で濃い世界を味あわせてくれました。