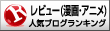『帰郷』は冬虫カイコさんの短編作品です。数年ぶりに帰郷する美幸。帰郷の理由は従姉妹の真喜の弔いです。真喜は同い年。昔から吉野家の法事など集いの時には母たちの手伝いをさせられ、親族からは二人ひと組として扱われていました。
手伝いをさせられるのは決まってふたり。同じ子供たちでも男の子たちはおじさんたちと宴の席に座っていました。
ここから先は、完全ネタバレで、私なりにあらすじをまとめ、そのあと感想を述べています。ご注意下さい。

母たちは、今手伝いをさせられるのはお嫁に行ってから役立つよ、と笑います。美幸と真喜は自由の少ない暮らしに少なからずうんざりし、互いの気持ちがわかる親友として、名前の入ったおそろいのマスコットを持ちます。
中3になったとき、真喜は父から、高校は近所に行けと命じられているといい、美幸は進学校に行くと言います。ふたりは高校を出たらどこかで一緒に暮らそうと約束します。それはたあいもない、実現性の低い約束でしたが、親友としての気持ちは重なり合っていました。
しかし3年後、親族の集まりで、県外の大学に進学するという美幸に親族は納得し、県外の専門学校に行きたいという真喜のことは「いっちょ前なことを言って」「やめとけ」とからかいます。ふたりの本心とは別に、ふたりは親族の中でポジションを与えられていたのでした。
美幸は、自分をうらやむ真喜についいらだって、進学校に行かなかったのも県外に出れないのも「自己責任でしょ」と言ってしまいます。すぐ言い過ぎを謝ろうとする美幸ですが、真喜は、どこへでも行ってしまえばいい、と突き放します。
それっきり。進学して就職した美幸が真喜の急逝の連絡を受けたのは一昨日でした。
精進落としの席で、親戚の男性は美幸にいつ地元に戻るのかと聞きます。反発して戻らないと本心を言う美幸に、女性たちは「おじさんは酔ってるから」ととりなし、母は謝るように促します。
日帰りするという美幸に、真喜の母は「美幸ちゃんが持ってるのか一番いいから」と、あのマスコットを渡します。
都会に戻った美幸は真喜に、ここでは誰も私たちを決めつけないし興味もない、と語りかけます。そしてビルの屋上で真喜と自分のマスコットを火に焚べて「どこでもないこの街でひとりにしてあげる」と、改めて真喜を弔います。

女が宴席のために働き、男は酒席を楽しむ、という情景は、時々漫画に描かれるような気がします。『ガンニバル』では、駐在の妻の有希が村人の宴会でお酌を強要されていたし、『蛍火の灯る頃に』では、進んで親族の食事の世話をする月に輝美が苛立つシーンがありました。私の実体験でもそういうことはよくありました。今の若い方たちはどうなのでしょうか?
この作品では、宴の席と、その場での親族たちの振る舞いは、閉鎖的な地方の名家の親族の中で、同い年の二人の女の子が、ポジションを決めつけられる象徴的な場と振る舞いとして描かれています。
二人が完全に大人たちから「2個いち」で扱われていた子供の頃は、二人の間では、明るく活発な真喜と、大人しくて慎重な美幸として、全く違う個性を発揮して、親友として二人は絆を育てていました。
しかし、高校生になって二人が「山高」と「山商」に分かれると、いままで二人を「2個いち」として扱ってきた大人たちは勝手に二人をキャラクターづけします。進学校から県外の大学にいって将来は女議員さんになるかもしれない優等生と、高校を出たら地元で就職していずれお嫁に行くだろうからかって構わないオンナノコとして色付けするのです。
実際、中学までは親友で、「高校を出たら一緒に暮らそう」とまで言っていた二人自身、山高と山商に分かれたら、付き合う仲間も変わって、距離ができてしまっているのを、自分たちでも感じています。
その中で、おじさんたちにからかわれて、ちょっと愚痴ってしまった真喜の言葉をきっかけに、美幸から自己責任こという厳しい言葉が発せられ、二人の距離は広がります。ただ、真喜の父は近くの高校しか許してくれず、美幸は勉強が好きだったし親も少し遠い進学校に進めさせてくれた、という違いだけだったはずなのに、二人のギャップは、簡単には越えられないものになってしまっていました。
ほんのちょっとした言葉の掛け違いから、そのギャップが明らかになる様が、鮮やかに描かれています。
そして真喜が突然亡くなった今。葬儀のために集まったはずの席で、「都会に行って出世する方の子」だった美幸のポジションはまた一方的に変更されます。「いつまでもふらふらしてないでさっさと地元に戻ってこい、とお説教されて素直に従う女」というポジションに、美幸は押し込められます。母や周囲の女性たちは自分の意見は何も言いませんが、少なくともその場では、男性の親戚の言うことを素直に聞いて頭を下げて、その場をやり過ごすことを要求します。
これは息がつまりそうです。私には耐えられそうにありませんが、本心はともかく、酔ってる人の言うことだし、ここでことを荒立てないで、とやり過ごさせようとする女性たちの気持ちはわかる気がします。母は、美幸が精進落としにも出ずに帰るのではないかと危惧したりもしているので、娘の気持ちはわかっているはずです。おそらく、母を含む女性たちも、酔って偉そうにする男の顔を潰さずに立てて、でも結局は自分の意志を通す強かさもあるのでしょう。そういう点も含めて「お嫁に行ったら役に立つ」立ち居振る舞いがあるのかもしれません。
でも、美幸はまだ若く、そんな強かさは身につけていません。都会に戻ってきた美幸は、誰にも注目されず気にかけられない孤独と引き換えに、誰にも決めつけられない自由を手に入れています。美幸が、早いうちに田舎の女衆のなかに取り込まれてしまった真喜を、どこでもない、美幸がいる都会でこそ、「ひとりにしてあげる」姿が心に染みます。真喜も、地元の狭い世界から、外の孤独だけれど自由に羽ばたける世界に出たかったはず、だからこそひとりにしてあげるのは「ここで」。
あと30年経っていたら、美幸が真喜を弔う気持ちもまた違うのだろう、と想像してしまうのは、多分私自身が歳を重ねているからだと思います。
若い美幸の青春の中での物語で、若くて真っ直ぐな心が愛おしい、と感じる作品でした。