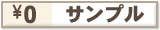『暗黒女子』は原作 秋吉理香子さん、作画 兄崎ゆなさんの作品です。秋吉さんの小説が最初にリリースされ、映画化もされています。
物語はサークルの定例朗読会から始まります。高校のたった6人のメンバーの部室にはふさわしいない華美絢爛な部室と設備と備品、丁寧で気取った言葉遣いから、お金持ち学校であることが伺えます。
ここから先はネタバレなのでご注意下さい。

今回のテーマは「前会長、いつみの死について」。いつみが亡くなって間もないのに挑戦的なテーマ。しかもこの人たち、朗読会をしながら同時に闇鍋もするのです。前回はそのなかにハイブランドの限定ウォッチまで入っていたということで、冒頭からこの学園の金持ちぶりが強調されます。
実はいつみの死についてはこのサークルのメンバーが関わっているという噂がでていることも最初に語られます。そんななかで、各自の書いた文章が次々と朗読されます。それぞれ、自分がいかにいつみと通じていたか、そして怪しい人物は誰なのか。理由を挙げて語ります。全員が順番に他人をいつみ殺害の犯人とします。
最後に現会長の小百合がいつみの書いた物語を読み上げます。実は「主人公」として人生を歩んできたいつみは周囲の人物を、自分を引き立てるサブキャストとして選んできたこと、そしていつみの死は自作自演、いつみは父の目を欺いて新しい人生を歩むことを選んだのだと告げます。さらに、閉会の挨拶として、光と影のように隣り合って生きてきた自分なのだから、いつみではなく自分が主人公となって生きて何がいけないと感じたこと、朗読会の前に訪ねてきたいつみを殺める機会があったこと、その後始末を闇鍋で処分できていた可能性があったことを示唆します。
パニックになる5人。冷笑的になだめる小百合。そんな中で部屋の明かりをつけた小百合は「主人公でいることって何てすばらしいのかしら」とうそぶき、閉会を宣言します。

このお話、女子校出身者にとっては臨場感があってものすごく楽しいです。各自のエッセイというか創作のなかで語られる女子校生活は金満なところは別として、生き生きと学園生活が描き出されています。少女たちが、自分こそが女王いつみの一番の理解者であると語る様も、それぞれとても真にせまっています。
学校の中に自分の意志で大理石をつかったプロ仕様のキッチンをつくってしまうとか、お気に入りの高級家具を置くとか、バザーのためにお小遣いで何百本もパウンドケーキを焼くとか、老舗割烹の娘とかブルガリアとの交換留学とか、特別な奨学金をもらった庶民の娘とか、ノーブルでゴージャスな非現実的の世界も、元少女の少女趣味を激しく満足させてくれます。
マカロナージュとか、お菓子とか紅茶の話がでてくるのも少女漫画っぽくてとても好き。やっぱり「文学サークル恒例、闇鍋の会。お皿によそったものは全部たべること」というコンセプトは、ストーリー上必要だとはわかるものの、どこか場違いではあります。
誰が本当のことを語っているのかわからない朗読もおもしろく、自分の目線でしか物事を考えられない思春期の身勝手さを現しているとおもいきや、5人で仕組んで犯人をわからなくするために画策しているとか、もうたまりません。
とっても、女性が書いたお話っぽいと感じました。兄崎さんの絵も、7人の少女たちが個性豊かに描かれていて魅力的です。もう夢中になってしまって、映画の特設サイトまで見に行っちゃいました(いまはサイトはクローズされているようです)。映画は見ていないのでコメントはできませんが、映画では人数は一人減って6人になってたみたい。確かにエピソードもキャラも弱い少女が抹殺されていて、さもありなんと思ってしまいましたが、漫画ではやっぱり欠かせないキャラです。
「主人公」いつみが、実は誰も眼中にないというのは好きですが、イケメン先生と恋に落ちたという話はちょっと不満です。このお話のなかで唯一女子校の人間関係外にのびている、もしくは伸びる可能性のあるエピソードなので、多分これが正しいのだと思いますが、主人公にはもっととっぴょうしのない鮮烈な理由で、皆の前から姿を消して欲しかったというのが正直な感想です。線の細い、(絵柄が)白っぽい感じの繊細そうな美青年との恋を貫き、親の目の届かないところで幸せな生活を築く、なんて。女子校がすべての狭い社会に生きている主人公としてあまりにも月並みではないでしょうか?そりゃあ主人公の座を奪われちゃうよ。秋吉さんがそうしたのって、わざとなのかなあ。あ。原作も読んでないので、原作と漫画は違うかもしれないですね。
こんな、女子校っぽくて(閉じていて)、サスペンスで、本当のことも誰を信じてよいかもわからなくて、そんななかでもフィクサーとして強い支配力を持つ人物がいるお話は大好物です!こんな感じの漫画があったら紹介してもらいたいな。