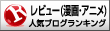『鵜頭川村殺人事件』は原作 櫛木理宇さん、漫画 河野那歩也さんの作品です。1979年6月にとある架空の村で発生した内乱事件を描いています。約900人の村で発生し、32人が死亡、187人が重軽傷という事件でした。
岩森明は、鵜頭川村で育った矢萩節子と結婚し、愛子という娘をもうけました。節子は早く亡くなり、鵜頭川村に葬られました。愛子が6歳になり、明は墓参りに訪れます。
ここから先は、完全ネタバレで、私なりにあらすじをまとめ、そのあと感想を述べています。ご注意下さい。

鵜頭川村は、少数の矢萩と多くの降谷、いくつかのそれ以外の家で形成されています。明治初期に田畑を売って工場を始めた矢萩が村に君臨しています。その中でも工場の社長の元市が事実上の村長、警察、裁判官をつとめ、出来の悪い息子の大助の数々の犯罪を揉み消しています。もうひとりの息子の隆也は降谷の家から有美を妻として迎え、ふたりは矢萩からも降谷からも浮いています。明の妻、節子は元市の姪で、節子の両親が既に鬼籍のために元市の家にステイしますが、高圧的で有美をぞんざいに扱う元市と親に反論しない隆也の態度に気まずさを感じています。
その夜、土砂崩れが起き、村は閉鎖された状態になります。そこで殺人事件がおき、若者たちは降谷辰樹を中心に、矢萩大助の犯行と決めつけて決起します。犯人と目された大助はプレッシャーに負け、ストレスから降谷の娘を襲います。人が駆けつけ、レイプは未遂に終わりますが、元市がその場に現れ、事件をもみ消します。若者たちはますます苛立ちを募らせます。
物資がはいらず物々交換が行われるようになった村の中で矢萩への売り渋りが始まり、矢萩もストレスをかかえます。矢萩vs降谷だけでなく、大人vs若者の対立も際立ち始めます。もう一件の殺人事件がおき、ついに若者たちは矢萩や大人の粛清を始めます。辰樹は、その内乱に紛れて、自分の出自を恨んで異母兄弟を犯そうとしていました。多くの血が流れた中で、明は辰樹の本当の目的を知り、愛子を狙われ、辰樹と対峙します。明は辰樹を殺しそうになりますが、すんでのところで思いとどまります。辰樹も毒気をぬかれて殺そうとしたことを弟に打ち明け、弟を殺すことはできなかったと呟きます。そこに自衛隊が到着し、内乱は制圧されるのでした。

1979年という年代がキーです。TVが完全に普及してから時間も経ち、都会の情報が田舎の集落にも伝わっていますが、まだ気楽にちょっと都会に行けるわけではない時代。全国的にはもう終わっている学生運動の核となった思想が、書籍として出版されている時代です。
地方集落で、家柄による確執というのは現在どの程度残っているのかは、首都圏で育ち、親類も大都市圏にしか所在していない私にとっては想像の範囲を超えます。私が25歳の頃は、長崎という都市出身の友人が「あなたたちにはわからないだろうけど、実家に戻るとこの年で『嫁ぎ遅れ』といわれちゃうのよ」と言っていて、愕然したことがあります。それから四半世紀が過ぎた今はどうなのでしょうか。男女の地位差や若者の発言力は変わっているかもしれませんが、経済を牛耳るものが実質司法も牛耳る構図は、いまでもあったとしても不思議はないと思います。
閉鎖された村のリアリティが、思わず冒頭に書いてしまった「架空の村」という言葉を言わせてしまうところで、この作品を読むとどうしても実録なのではないかと思ってしまいます。そういえば、この作品はドラマ化もされたみたいで、元となった事件があるのかどうか調べようとしたら「鵜頭川村事件」の検索ワードに「元ネタ」が出てきました。みんな気になるのですね。
学生運動がもう下火になった時代に、地方の若者たちが東京に強烈な憧れを持っていたという設定は、1979年にはしっかり物心あった人間からするとどうなんだろう、という気もします。その時代は「テレビで都会と自分のギャップを知ってしまった」と言うにはちょっと時代が新しすぎるのではないか、と感じてしまうのです。櫛木理宇さん、若い方なのではないか、と調べてみたところ、意外と同世代の方でした。ご出身は新潟のようですが、ご自身は閉鎖的な地域で育ったというわけではなさそうです。と、すごく作者さんのことが気になってしまう作品です。
しかし、内乱を先導している辰樹がもくろんでいるのは、旧い社会の打倒だけではありません。この村にとって、東京から来てたかだか数年間ここで暮らしただけの「よそ者」であると同時に、「狩られる者」となった矢萩の関係者である明には、それを見極めることができます。鵜頭川村には、男一人しか授からなかった男親は、他所の男の種をもらって息子をもう一人妻に産ませ、自分の息子として育て家の断絶を防ぐ、という忌まわしい慣習があったのでした。辰樹は次男で、ずっと父に認められたいと思って生きてきて、兄が亡くなったときには自分が父を支えて生きていくと誓ったのに、結局父は辰樹を顧みることなく、長男が亡くなった失意で死んでしまったのでした。矢萩が、とか、大人が、ということではなく、最後まで父の愛を求めてそれが叶わず、何も知らずに自分の実父に長男として愛されて育てられた異母弟への暗い思いを抱えた男、それが辰樹でした。弟である和巳に「弟を殺せなかった」と話しかけるところはやや唐突に感じました。育ての父に愛されなかったことに対する深い絶望は感じるのですが、実の父に対するこだわりはなかったし、そのこだわりがないことに対しては違和感がなかったので、幸せに育った異母弟に対するやっかみや愛やこだわりはあまり感じられませんでした。状況的にそういう気持ちになるだろうことはわかるのですが。サスペンスで、辰樹の気持ちはクライマックスまで伏せられているのと、状況自体が複雑なのでむしろこの描写でないと冗長になってしまうかもしれません。これは漫画の描写ではなく読者が感じるべきことでいいように思います。和巳が辰樹の頭を支えて、辰樹が愛子に「俺の親も君のみたいなら良かった」と言うシーンはとても好きです。
一方で、明は鵜頭川村とは違う出自を持って、トラウマを抱えています。子供の頃から、「悪いことをするとエイキチが来る」と母に言われて育ったのでした。エイキチが何なのか、何故オニではなくエイキチなのか、明にはわかりません。でも、子供の頃から、エイキチが来ると言われると、明は恐ろしい気分に襲われるのでした。内乱の中で人質にとられた愛子を取り戻そうとして辰樹と暴力で対峙したときに、エイキチは来るのではなく、誰の中にもエイキチがいて、排他的で攻撃的になり自分の目的のために他者を排除してもよいと思ってしまったとき、エイキチが表面にでてきて理性をすべて封じて狂気に捉えられてしまうのだと気づきます。それに気づいた明は、愛子の眼の前で辰樹を殺すことなく冷静になることができたのでした。
エイキチの描写を見ているときに、河野さんの『監禁嬢』の、父親の恐ろしい笑みが心に蘇ってきました。『監禁嬢』の感想を書いたときにはラストがあまりしっくりこないでいたのですが、この作品で「エイキチ」の表現を見ていたら、急に『監禁嬢』にも共感してしまいました。エイキチが誰の心の中にもいる悪魔のような他人を排除する気持ちと同じように、人を不幸に陥れることを喜ぶ悪魔のような気持ちも誰の中にもあるのかもしれません。この作品の表現を見て他の作品の解釈まで変わってしまうほど、明の中にいるエイキチの表現が、胸に染み込んできました。『監禁嬢』の岩野と、岩森明が、自分の感情をコントロールする力が少し弱い男、という共通点があったので、余計に共通点を感じてしまったのかもしれません。最初は河野さんの作品だと気づかずに「見たことある絵だな」ぐらいの気持ちで読み始めたのですが、この作品自体にしっくりできるところがあったことからも、河野さんのべつの作品への解釈が変わったことからも、読めてよかったです。